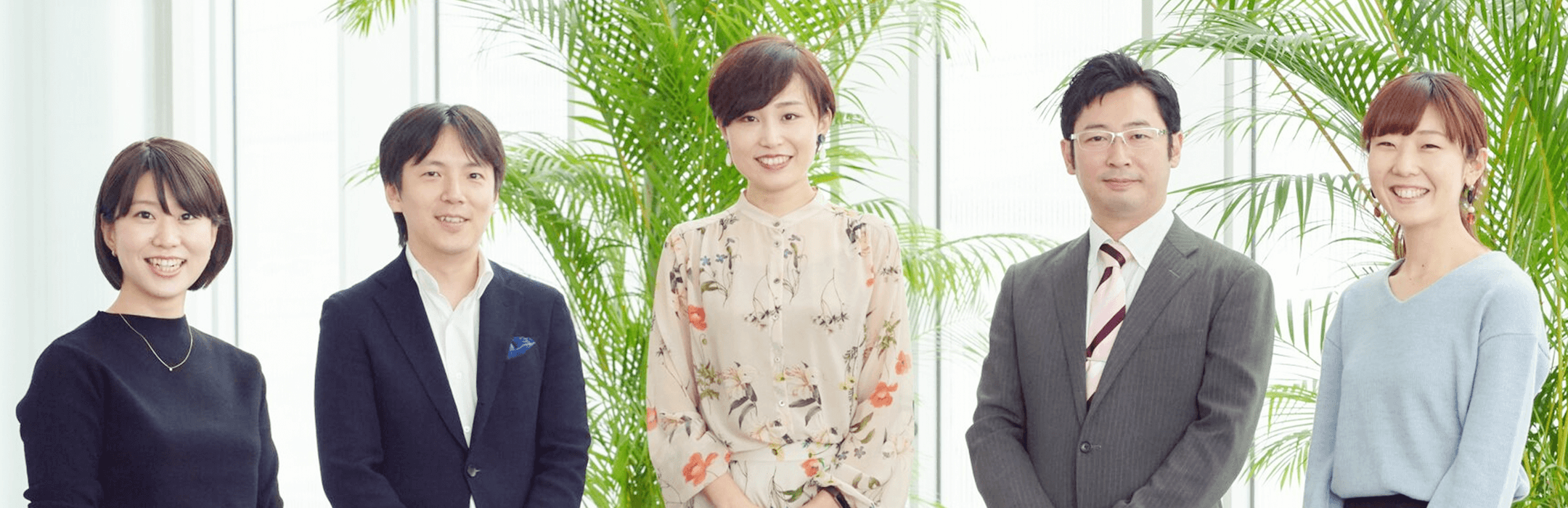丸井グループの
テクノロジーを振り返る。
花崎:私は現在エポスカードに所属していますが、IC付きのVISAカードが即時発行できるというのは丸井グループのテクノロジーを象徴しているように思います。他社では今日現在でもほとんど実施できていないことですし、その場でクレジットカードを発行し、使っていただけるというのは非常に大きいですね。
中村:私は入社3年目(座談会時点)ですが、入社当時はそれがとても当たり前なことだと思っていました。ただ、外部の商業施設に出店する「マルイのシューズ」ショップで働いた時に、そこではできないということを自ら体験して、今まで当たり前だと思っていたことが「実はすごいこと」だと知りました。そして、その裏には当然のようにテクノロジーがありました。
花崎:カードの申込も今はタブレットですが、以前は紙でお客さまに記入していただいて、カードセンターで入力するというフローでした。当然紙を失くしたら個人情報なので大問題という感じでしたね。
生形:私はエポスカードができた時に入社しましたが、入社してすぐエポスカードセンターに配属されました。カード発行機の部屋というのがあって大きな音を立てながらカード発行をしていました。その当時は画期的でしたが、10年経過した現在も他社は依然としてそのような状況のようです。エポスカードはその後も進化し続けています。
木村:入会申込用タブレットの導入も画期的ですが、もう少し遡ると「ネット申込」というのは売場にとってだけでなくお客さまにとって相当利便性が上がったように感じます。
小林:口座振替も昔はメガバンクしかできませんでしたが、その他の銀行などと提携してデータのやりとりができるようにすすめています。今まではカードをつくるのと口座振替を登録するのは別アクションでしたが、今はタブレット一つでできるようになっていますね。
中村:それも他社と比較してすすんでいるところです。カード発行と口座登録が別で、改めてハガキを送るところも多いようですから。
天崎:社内にいると自社のすごさがわかりにくいのですが、外から眺めると先進的と言いますか、進歩しているように感じます。いつの時代も最新を保っているという印象です。
中にいると気づかない
丸井グループの先進性。
花崎:学生時代、マルイのカードは「初めてのカード」という印象があったのですが、それは店舗があって申込みやすいからだと思っていました。もちろんそれもありますが、実際入社して知ったのは与信の仕組みが特殊で、利用実績に基づいて限度額が変わるシステムが、結果的にお客さまに喜んでいただく上で非常に機能しているということでした。
木村:最初のご利用限度額を低くし、ハードルを下げることで入口を拡大するという仕組みですね。ノウハウを持っているから結果として貸倒れも少なくなります。
生形:お客さまからすると「金融の会社」というイメージはあまりないかもしれませんが、そこに大きな投資をしてきていて、スピード感を持って一つずつ改善してきています。ウェブチャネルではECと店舗の在庫を連動させたり、取引先の倉庫と在庫データを連携させたりすることでお届けまでを早くしたり、売り切れをなくしたりすることができています。
木村:今ではWebと店舗どちらで売れてもいいという感覚がありますが、昔は店舗側に「売上を取られる」という意識があり、啓蒙活動を10年くらいかけてやってきました。
花崎:Webを中心に展開されているテナントで、リアルは「体験ショップ」と位置付けているテナントが、他の商業施設では「リアルは体験の場」ということになかなか理解を示してくれないという話をしていました。マルイは自社でも体験ストアをおこなっているので話がすすみやすいと言われた時に「マルイってすすんでいるんだ」と感じました。

グループとしての強み。
外部と内部の使い分け。
天崎:それらはシステム会社であるM&Cシステムがグループ内にあることも大きいと思います。生の声を聞きながら各社のニーズを捉えているということの表れです。
小林:他の会社より「早い」と言われていますよね。
天崎:技術力だけ見れば他のシステム会社の方が上ということもあると思います。しかし、単にシステムを導入するにしても「何のためにやるのか」ということを理解しているかどうかは、非常に大きな違いです。作業のようにおこなっていくとできることに限界があります。

木村::以前外部のシステム会社でアプリの開発をしようとした時、システムには詳しいけれど「お客さまニーズ」をなかなか汲み取ってもらえないということがありました。M&Cシステムは売場経験者が多いということもあって「言わずもがな」ですすめることができました。それは非常に大きな強みです。
生形::逆に専門家の力を借りればもっとできることもあるかもしれないと思うこともあります。
天崎::そこも含めてM&Cシステムの役目かなとも思います。プロの専門家と社内の人たちをつなぐパイプ役にならなければと思っています。
花崎::外部とうまく連携するのか自分たちでやるのか、うまく使い分けていく必要はありますよね。
木村::そうですね。全部自分たちでできればいいけどそうではないからオープンイノベーションが必要になってくるのだと思います。
テクノロジーの
さらなる可能性。
木村:エポスカードのビッグデータをもっと使えないか考えています。エポスと通販と店舗のデータがすべて繋がるときっと面白いことができるような気がします。
花崎:国内で言えば相当莫大なデータを持っている方ですから、それらをどう使うのかということがとても大切です。お客さまの心を動かすためにAIなども使いながら人間の目では気づかないことを実現していけたらと考えています。
生形:サードパーティ(ユーザがアクセスしたWebサイトとホストドメインが異なるサイト)のデータも活用してエポスのデータと掛け合わせることもできますからね。
花崎:あとは、ECにAI設定を導入できたらいいなと考えています。丸井グループにはリアル店舗で集積した接客のノウハウがあるわけですから、リアルでおこなっている接客をWebでも体感できるようにできたら素敵ですよね。
生形:オムニチャネルの構想を少し話すと、ヒューマンパワーは資産ではありますが、お客さまの中には店員が寄ってくることを嫌がる方もいます。コミュニケーションを面倒と考えたり避けたりする人にとっては、Webはすべて自分でできますし簡単でもあるので「Webの良さ」を残すことも重要です。接客を避けてWebにきたのにそちらでレコメンドされては元も子もないですから。そこのバランス感覚を持ち続けられるようにしていきたいですね。
花崎:Webの店員は自分で選べたらいいかなと思います。お節介な店員もいれば、必要な時にだけ声をかけてくれる店員もいる。リアルの店舗では店員は選べませんが、自分の好みに合った人が接客してくれたらいいなと思います。リアルだと「どうでもいい会話」が「寄り添う」ということだったりもしますよね。
中村:ECが益々進化していく中で「逆にリアルだよね」という流れも起きつつあります。Webでお客さまの利便性を向上した後にリアルが再定義されるわけです。リアルを持っている丸井グループがどのような「お役立ち」をできるのかということを今は考えています。リアルだと試着はできるけれど商品数を増やせば物が溢れかえる。一方で、Webは商品数に制限はないけれども試着はできない。だからこそ双方をシームレスにしてお客さまにとって「一番いい状態」をつくり出していくということが求められます。
花崎:アメリカだとリアル店舗が相当潰れていますね。
中村:「リアル発の店舗が潰れていて、Web発の企業はリアルに出ていきたい」というのがトレンドです。日本でも若干それが起きようとしています。Web発でまず「ファン」を持ち、実際に「会いたい」「見たい」という流れを作っていくわけです。
生形:ベースがオンライン(Web)で「プラスの価値」を発揮するのがオフライン(リアル)ということですね。
中村:そうです。軸足はオンラインというイメージです。
小林:一方で便利にしようとすればするほど情報は漏れやすくなりますから「セキュリティ」も同じくらい重要視する必要はあります。お客さまに安心してご利用いただけるということは今後益々求められるようになっていきます。すごく便利でも一つ漏れたらそのサービスは「なし」になってしまいますから。
お客さまのために
できること。
花崎:カード会社だと「不正検知」がわかりやすいと思います。時間・場所・金額などをもとにシステムが悪用を検知してカードの利用を止めるというものです。例えば、東京在住なのにフロリダで何百万円もの利用があった場合などですね。しかし、現時点でその精度は100%ではありません。ある程度ラインを決めるわけですが、1件の悪用を止めようとすると正常な利用をいくつか止めてしまうわけです。これもAIなどで分析していければ、お客さまの利用を阻害しない仕組みの導入ができると思います。
中村:私はパーソナライズしていく必要があると思います。さまざまなサービスが無料になり、お金を使う意味自体も変わりつつある中、「何故お金を使うのか」に対する一つの答えとして「私のもの」ということが挙げられます。例えば、これまでデータは「企業がマーケティングのために活用するもの」という認識でしたが、ヨーロッパでは「データはお客さまのもの」という価値観が主流です。それを公開するのかしないのか、お客さまが決められるようにしようということです。
花崎:連携していくということも大切ですね。「お店とシステム」「物流とEC」これらをつなげていく。丸井グループは「何業」でもなくて「お客さまのために挑戦をしていく会社」ということなのでしょうね。

木村:それらを実現していくためにも「想い」が大切なように感じます。丸井グループの組織風土でもある「できる、できない」ではなく「どうやるか」という発想です。企業やお客さまのために「やりたい」という想いが先にあるからこそ、実現に向けて試行錯誤ができる。丸井グループの歴史を振り返れば、お客さまのために業態すらも変えてきたわけですから。

※社員の所属や担当業務は2018年3月時点の情報です